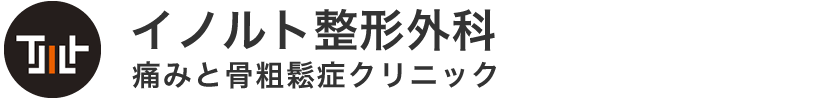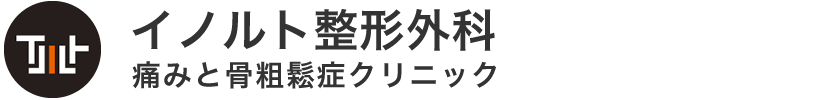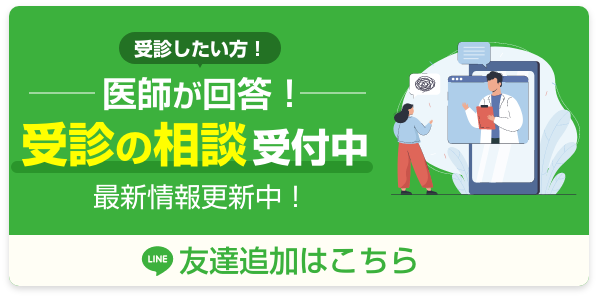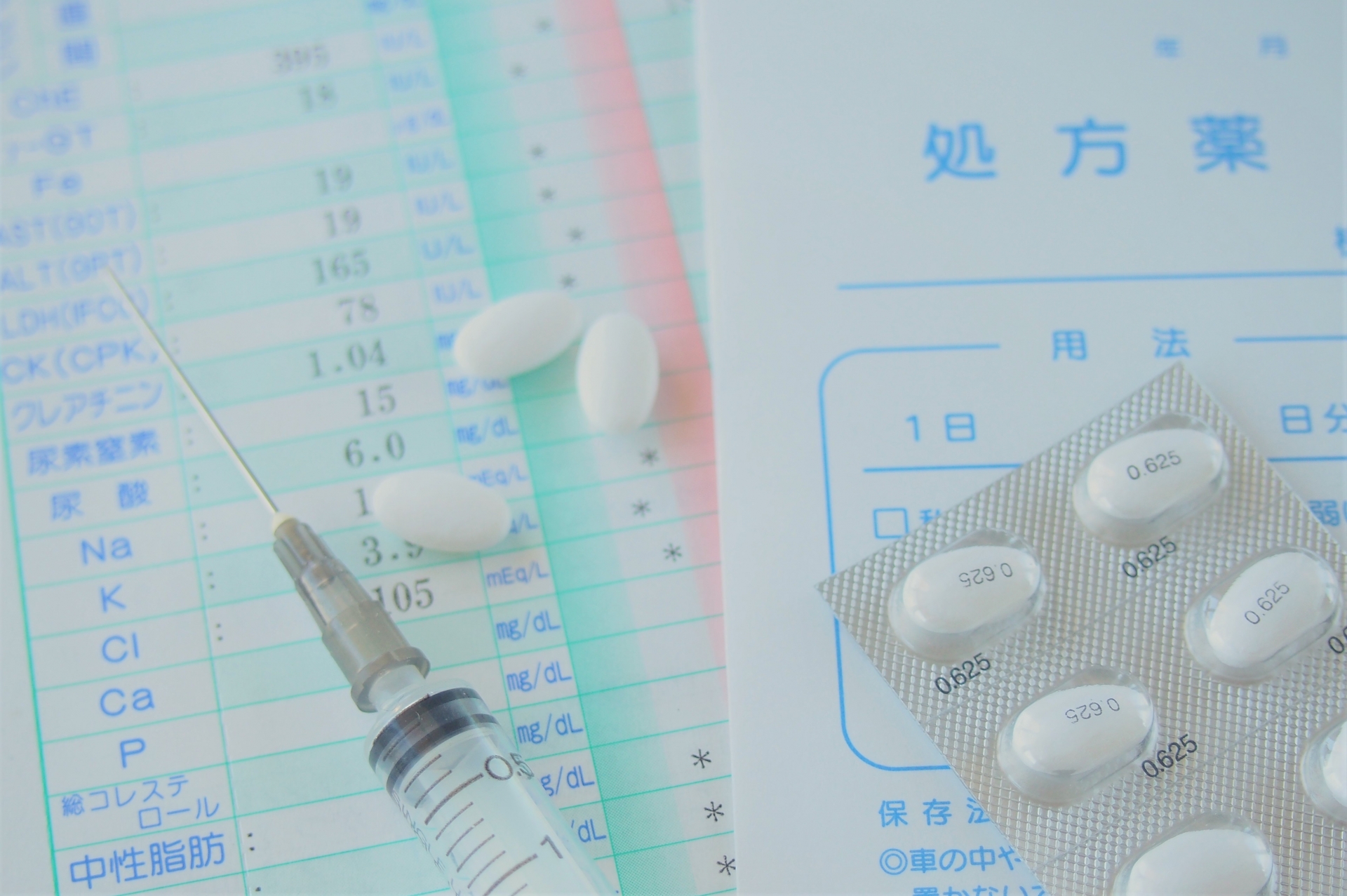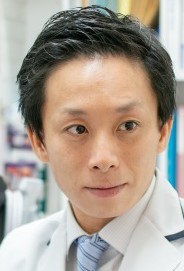変形性膝関節症
変形性膝関節症とは

変形性膝関節症とは

変形性膝関節症では、加齢などさまざまな原因により膝の関節の軟骨が擦り減ったり、半月板が痛んだり、骨の変形が起きる病気です。
関節炎をおこし、徐々に関節の変形が進み、慢性的な痛みや関節可動域制限により歩きづらくなるなど日常生活に支障をきたします。
患者数は800万人以上いるといわれ、加齢とともに膝関節の変形が進行し、痛みで徐々に歩けなくなり、要介護状態になってしまいます。
変形性膝関節症は膝関節軟骨には神経がないため、痛みは関節の袋(関節包)・半月板・靱帯・骨髄・骨膜などにある神経(自由神経終末)に侵害受容性疼痛として伝わります。
膝関節軟骨が劣化(変性)・破壊され、荷重や衝撃に対する緩衝力が失われると、物理的刺激が一次痛と呼ばれるチクチクとした短く鋭い痛みとして脳に伝わり、痛みの部位と強度を認識することになります。
変形性膝関節症による組織の障害により、膝関節内ではさまざまな物質が作られ、二次痛と呼ばれる遅れて出てくる鈍い痛みとして脳に伝わり、不快感や不安感などを引き起こします。
変形性膝関節症の原因は?

加齢
膝は年齢とともに徐々に擦り減っていきます。
70代では2人に1人が変形性膝関節症といわれています。
この場合は軟骨がすり減る速度は左右同程度の場合がほとんどです。
膝の骨折・靱帯損傷・半月板損傷(スポーツ・交通事故など)
膝の骨折、特に関節内に至る骨折では軟骨部分の損傷や段差を残して治る場合が少なくありません。
また、前十字靱帯など膝の靱帯を損傷して膝の安定感がなくったり、軟骨を守るクッションの役割を果たす半月板が損傷した場合、軟骨に掛かるストレスが大幅に増えます。
そのため、怪我をした側の膝では、中長期的に膝の軟骨のすり減りが大幅に進行しやすくなり、若年者でも変形性膝関節症になってしまう場合があります。
体重が重い方
体重が重い方は膝の軟骨に掛かる負担が体重が軽い方よりも大幅に増え、通常よりにも速い速度で擦り減っていき、早い段階で変形性膝関節症になりやすくなります。
通常は左右とも均等に擦り減っていきます。
O脚の方
O脚の方は膝の内側に掛かる負担が大幅に増えるため、体重が重い方と同様に膝の軟骨がすり減り、変形性膝関節症になりやすくなります。
O脚により内側の軟骨がすり減ると、よりO脚は進行して変形性膝関節症は進行しやすくなります。
激しい運動
登山やジャンプ競技などは膝の軟骨のすり減りを速める場合があります。
長年膝を酷使した運動をしている方では、運動していない方と比べると早く軟骨がすり減り変形性膝関節症は起こしやすくなります。
ほとんどの場合で、両側とも変形性膝関節症の程度は同じような状態になります。
化膿性膝関節炎
糖尿病などにより免疫力が落ちた結果、細菌が血液に乗って膝関節にやってきたり、膝にヒアルロン酸注射などを繰り返し行っている間に、稀に住み着いてしまう場合があります。
抗生物質の点滴や手術による洗浄が必要になりますが、治療が遅れた場合、関節内の著しい炎症が原因で軟骨などが破壊されてしまい、細菌感染が治った後も変形性膝関節症になってしまい痛みが残ってしまう場合があります。
感染の多くは片側の膝のみになるため、変形性膝関節症も片側になる場合が多いです。
変形性膝関節症の症状・所見など

変形性膝関節症の初期は、歩き始めや椅子から立ち上がり、しゃがむ動作や階段を下りる際に膝の内側に痛みが出てきます。
進行してくると、平地歩行でも膝の痛みが出て、正座も難しくなります。
膝関節の骨の変形が進むと、膝が伸びなくなり、O脚が目立っていきます。
診察では膝の内側を押して痛みがないか、動きが悪くなっていないか、水(関節液)が溜まってないかなどを診ます。
関連ブログ:【膝の違和感】膝を伸ばしたときに出る痛み以外の症状と原因について解説
変形性膝関節症の検査・診断
基本的に
- レントゲン検査
- 超音波検査
- MRI
などの検査で診断をします。
レントゲンでは軟骨の幅が狭くなっていないか、変形がないか、O脚になっていないかなど、変形性関節症の度合いも1期~4期で評価します。
超音波検査では関節液が溜まっていないか、炎症が起きているところはどこなのか、軟骨や半月板は痛んでいないかなどを診ることができます。
初期や骨壊死や半月板損傷や靱帯損傷などを合併している可能性がある場合はMRIでも評価する場合があります。
その他、関節リウマチ、単純性関節炎、化膿性関節炎、痛風や偽痛風による結晶性関節炎などと見分ける必要がありますが、疑わしい場合は血液検査や関節液の検査を行います。
変形性膝関節症の治療とは
適度な運動習慣をつける
変形性膝関節症による膝の痛みを改善するために大切なのは、適度な運動習慣をつけることです。
膝の痛みがあると普段から安静にしてしまいがちですが、ずっと体を動かさずにいると膝周囲の筋肉が衰えやすくなります。
すると、膝関節のクッションの役割を担っている軟骨に負荷が集中してすり減りやすくなり、変形性膝関節症がさらに進行してしまうという悪循環に陥ってしまいます。
また、運動不足だと体重も増加しやすくなり、膝への負担をさらに増加させ、変形性膝関節症を悪化させる一因となります。
このように安静にしすぎることは、膝の痛みの悪化に繋がります。膝の痛みでお悩みの方は無理のない範囲で少しずつ運動習慣をつけていくようにしましょう。
OARSI(国際変形性関節症学会)や日本整形外科学会、AAOS(米国整形外科学会)が発表した変形性膝関節症の診療ガイドラインでも、変形性膝関節症の治療法として筋力強化訓練や膝の可動域拡大訓練(曲げ伸ばしできる角度を広げるためのストレッチ)、有酸素運動を行うことを推奨しています。(*2, 3, 4)
そこでここからは、自宅でできる膝の痛み改善に効果的な運動をいくつかご紹介していきます。
大腿四頭筋の筋力トレーニング①
大腿四頭筋(だいたいしとうきん)は太ももの前側にある筋肉で、膝関節を支える役割を果たしています。
そのため大腿四頭筋を鍛えることで膝関節への負担分散が期待でき、膝の痛みの改善が見込めます。
変形性膝関節症の膝の痛みに対する大腿四頭筋の筋力トレーニング効果を検証した研究においても、トレーニングを行わなかったグループに対して、トレーニングを行ったグループの方が膝の痛みをはじめとした症状が改善されたことが報告されています。(*5)
そこで本記事では、日本整形外科学会も推奨している、変形性膝関節症による膝の痛みに効果的な大腿四頭筋を鍛える運動方法をいくつかご紹介いたします。
(参照:変形性ひざ関節症の運動療法)
- 椅子に腰掛けます。
- 右膝を、脚が床と水平になるまで伸ばし、ゆっくり息をしながら5〜10秒間その状態をキープします。
- 右足をゆっくり元の位置に戻します。
- 反対の脚についても同様に行います。
大腿四頭筋の筋力トレーニング②
- 膝を伸ばして、床に座ります。
- 右膝の下に丸めたタオルなどを置き、丸めたタオルを押しつぶすようにします。
- 5〜10秒程度、ゆっくり呼吸をしながらその状態をキープします。
- 力を抜きます。
- 反対の脚についても同様に行います。
トレーニングを行う回数については、膝の痛みの程度などによって異なってきます。
そのため自宅などでトレーニングを行う場合は、事前に整形外科を受診し、適切なトレーニングの内容や実施する回数についてもご相談いただくことをおすすめします。
膝のストレッチ
膝の痛みを避けようとして体を動かさないでいると、筋肉は硬くなってしまいます。
筋肉が硬くなり柔軟性が失われると、膝関節への負担も増してしまい、膝に痛みが生じやすくなります。
そこでここからは、変形性膝関節症による膝の痛みに効果的とされるストレッチ方法をいくつかご紹介いたします。
ここでご紹介するストレッチ方法についても、日本整形外科学会が推奨するトレーニングになります。
(参照:変形性ひざ関節症の運動療法)
まずは膝の柔軟性を保ち、膝の痛みの予防・改善効果が見込めるストレッチ方法をご紹介します。
- 床に脚を伸ばして座り、右のかかとの下にタオルなどを敷きます。
- かかとをゆっくりと引き寄せ、膝をできるだけ曲げます。
- かかとをゆっくりと元の位置に戻し、膝を伸ばします。
- 反対の脚も同様に行います。
前脛骨筋と腓腹筋のストレッチ
次に、前脛骨筋(ぜんけいこつきん)と腓腹筋(ひふくきん)という筋肉の柔軟性を保つためのストレッチをご紹介します。
前脛骨筋は脛骨(けいこつ:すねの骨)と足首をつなぎ、すねの前側に位置する筋肉です。
主に足首を引き上げたり反らす際に使われるほか、土踏まずを維持する役割も担っています。
この前脛骨筋が維持している土踏まずは、歩く際、足が地面に着いたとき(接地時)の衝撃を吸収するクッションのような役割があります。
そのためこの前脛骨筋が衰え土踏まずがなくなると、足の接地時の衝撃が吸収されず、膝への負担が増してしまいます。
また、腓腹筋はふくらはぎの筋肉のひとつで、地面を蹴る際に重要な役割を果たします。
腓腹筋が衰えると、膝や足首の動きが悪くなり、不安定になってしまうため、膝の動きがブレやすくなり、膝への負担も増してしまいます。
ここでは、前脛骨筋と腓腹筋を同時に柔らかくするストレッチをご紹介いたします。
- 床に両脚を伸ばして座ります。
- つま先を前側にゆっくり伸ばします。
- つま先を手前側にゆっくり引き寄せます。
- 2〜3を10回程度繰り返しましょう。
ウォーキング
先述でもご説明したように、ウォーキングなどの有酸素運動も、変形性膝関節症による膝の痛み改善に有効です。
ウォーキングを行うことで膝関節を支える膝周囲の筋力向上に加えて、脂肪燃焼による体重増加防止も見込めます。
すると膝関節への負担も軽減でき、変形性膝関節症による膝の痛み予防にも繋がります。
ウォーキングを行う際は、週2〜3回、1日30分程度を目安にしつつ、膝の痛みがある方は無理のない範囲で行うようにしましょう。
水中ウォーキング
変形性膝関節症による膝の痛みに効果的な有酸素運動としては、水中ウォーキングも挙げられます。
水中では浮力が働くため、膝関節への負担が軽減できる上、水の抵抗によりゆっくり歩くだけでも全身運動となり、多くの筋肉を鍛えることができるため、より一層の脂肪燃焼効果も見込めます。
エルゴメーター
エルゴメーターとは固定式自転車のことで、このエルゴメーターを活用したトレーニングも変形性膝関節症による膝の痛みにお悩みの方にはおすすめです。
エルゴメーターは負荷の調整もできますので、ご自身の体調や身体能力、膝の痛みの程度に合わせて無理なくトレーニングを行うことができますし、室内でのトレーニングが可能なため、天気に左右されたり、交通事故に遭うといったリスクもありません。
適切な体重管理を行う
膝の痛みを改善するためには、適度な運動を行うとともにバランスの取れた食生活を送り、適切な体重管理を行うことも大切です。
先述でも解説したように、体重が増加すればその分膝への負担も増し、膝の痛みが出やすくなります。
体重を1kg減らすには、7200kcalのエネルギーを消費する必要があるとされています。
せっかく運動をしていても、それ以上に暴飲暴食をしては体重が増加し、膝への負担が増えてしまいます。
膝の痛みを改善するためには、適度な運動とバランスの取れた食事にあわせて気をつけ、しっかりと体重管理していくことが大切です。
関連ブログ:膝の裏が痛いのはなぜ?歩きすぎが原因?おすすめストレッチ方法を紹介
保存療法
ここまで、膝の痛みを改善するために、自らでできる対処法をご紹介してきました。
しかし膝に痛みがある場合に大切なことは、まず整形外科を受診し、適切な治療を行うことです。
膝の痛みを抱える方の多くは「歳のせいだから」と整形外科を受診せずに放置し、膝の痛みを悪化させてしまいます。
すると将来、歩く・立つといった基本的な動作が困難になり、介護が必要になる可能性を高めてしまいます。
このような事態を防ぐためには、膝の痛みを感じたときに整形外科を受診し、適切な治療を開始することが大切です。
先述の「膝の痛みの原因」でも述べたように、日本における変形性膝関節症の患者数は2530万人にものぼっています(*1)。
よってここからは、変形性膝関節症による膝の痛みに対する治療をご紹介していきます。
変形性膝関節症による膝の痛みを改善するための初期治療としては、まず「保存療法(主に手術以外の治療)」を行うことが一般的です。
ここからは保存療法ではどのような治療を行うのかご紹介します。
運動器リハビリテーション
膝の痛みに対する保存療法の1つ目は運動器リハビリテーションです。
運動器とは、骨や関節、筋肉、神経など、体を支えたり動かしたりする組織や器官のことをいいます。
運動器リハビリテーションは、このような運動器に疾患がある方に対して、理学療法士による徒手療法や運動療法をはじめ、物理療法、装具療法などを用いて身体機能や生活動作の改善を行っていく治療法です。
それぞれ解説いたします。
徒手療法
徒手療法とは、膝の痛みなどの症状がある箇所を手指にて圧迫したり、摩擦することによって症状の改善を目指す治療法です。(*6)
運動療法を行う前に固まった筋肉をほぐすために行われることもあります。
運動療法
「膝の痛み改善のためにできること」でも述べたように、適度な運動は変形性膝関節症による膝の痛みに効果的です。
適切な運動を行うことにより、膝周囲の筋肉が鍛えられて膝の安定性が増し、膝の痛みの改善が見込めます。
とはいえ、過度な運動や間違った方法で運動を行ってしまうと、症状が悪化しかねません。
リハビリ専門の国家資格である理学療法士(患者が自立した生活を送れるようサポートするリハビリテーションの専門職)のいる整形外科では、理学療法士による指導のもとトレーニングができるので、筋力トレーニングを適切に行うことができます。
しかし、変形性膝関節症は慢性的な疾患ですので、通院時以外も自主トレーニングを継続することが大切です。
医師や理学療法士の指示・指導を参考に、先述の「膝の痛み改善のためにできること」にてご紹介したトレーニングなどを日頃から継続することで、膝の痛みの改善に対し、より高い効果が期待できます。
物理療法
物理療法では、患部を温めて血行を促進することで回復が早まるのを期待する温熱療法などを行い、膝の痛みを和らげることを目指します。
組織修復を促す超音波治療(音波を用いて膝痛などの症状緩和を目指す治療法)を行うこともあります。
装具療法
装具療法では、膝のサポーターや足底装具(インソール)などを用いて膝への負担を軽減させることを目指します。
薬物療法
薬物療法とは、薬を用いて膝の痛みや炎症を抑える方法です。
変形性膝関節症を抑える治療としては、外用薬、内服薬、注射などがよく用いられます。
外用薬には塗り薬と貼り薬があり、処方される方の体質や生活環境に合った薬を用います。
膝の痛みなどの症状が軽い場合は基本的に外用薬を、症状が重い場合やなかなか改善しない場合は、外用薬と内服薬を併用することが多いです。
最近では、「ロコアテープ」という変形性膝関節症専用の湿布や、「サインバルタ」という変形性膝関節症用の飲み薬なども認知されてきており、膝の痛みがなかなか改善しない方はこういった薬を試してみるのもひとつの方法になります。
また、もともと関節内に存在し、関節のクッション材としての役割を持つ「ヒアルロン酸」を関節内に注射する方法も薬物療法の中でよく用いられます。
手術療法
上記にてご紹介した保存療法を一定期間行っても症状が改善しない場合や、症状が重く、日常生活に支障が出ている場合は、手術による治療を検討することがあります。
変形性膝関節症治療のための手術方法には、関節鏡視下手術、骨切り術、人工膝関節置換術があります。
変形性膝関節症が原因で、日常生活がままならないほど膝が痛む場合は、こうした手術も視野に入れて検討すべきでしょう。
関節鏡視下手術
関節鏡視下手術とは、膝に数箇所小さな穴を開けて関節鏡(細い管の先にライトと小型カメラのついた関節用の内視鏡)を差し込み、関節内遊離体(関節内の軟骨などの欠片)などを取り除く治療法です。
半月板(膝関節にある軟部組織)が断裂している場合は半月板の縫合や切除を、軟骨が損傷している場合は軟骨移植やマイクロフラクチャー(軟骨に小さな穴をあけることで血液・骨髄液を生じさせ、治癒を促す治療法)を行うこともあります。
骨切り術
骨切り術は、膝の変形が強い場合に脛骨(けいこつ:すねの骨)や大腿骨(だいたいこつ:太ももの骨)の一部を切ることで、症状を和らげる治療法です。
O脚やX脚などの膝の変形がひどい場合、膝の内側または外側に荷重が偏ってしまい、荷重が多くかかる側の軟骨がすり減りやすくなり、痛みをもたらします。
そこで骨切り術では脛骨や大腿骨の一部を切り、膝関節への荷重の偏りを修正することで、膝の痛みの改善を目指します。
この方法では自身の骨や靭帯を温存できるため、治療後は膝の曲げ伸ばしが以前と比較的同じ感覚でできるようになり、術後、骨が癒合したあとは運動などに制限もかかりません。
ただし骨切り術は、金属のプレートで骨を固定する手術と、プレートを抜く手術の計2回、手術を行う必要があります。
また、合併症として、まれに術後に骨がうまくくっつかず、骨が折れたままの状態になってしまう場合もあります。
加えて、骨切り術は高齢の方や筋力の衰えている方、膝の内側と外側が両方とも悪い方などには適していません。
さらに靭帯が切れてしまっている場合は靭帯を再建しなければ手術はできない、O脚やX脚などの脚の変形が極端に強い場合も手術を行えない、といった制限もあります。
人工膝関節置換術
人工膝関節置換術は、傷んだ膝関節を金属などでできた関節に入れ替える治療法です。
高齢者にも適した治療法で、治療後は膝の痛み軽減や膝の可動域(曲げ伸ばしできる角度)の改善、O脚・X脚の改善が期待でき、旅行や買物などの日常的な動作が以前のようにできるようになります。
ただし、人工膝関節置換術は膝関節内の骨や軟骨を切除し、靭帯も切除する場合が多いので、個人差はありますが人工関節が身体感覚に馴染むまで1年程度の期間が必要とされています(靭帯を温存する人工関節置換術や単顆型人工膝関節置換術もあります)。
またデメリットとして、術後は激しい運動や正座ができないことや、術後感染により再手術が繰り返し必要になるケースがあること、深部静脈血栓症が高い確率で起こることが挙げられます。
加えて、人工関節の寿命(一般的に25〜35年)に応じて再手術が必要になる可能性もありますが、人工関節の耐用年数は技術の発展に伴い徐々に伸びており、半数以上の方は再手術不要との報告もあります。
その他の治療法
バイオセラピー
ここまで保存療法と手術療法についてご紹介してきましたが、昨今では第三の選択肢としてPRP療法やPFC-FD™療法、脂肪由来幹細胞(ASC)治療といったバイオセラピーが活用され始めています。
バイオセラピーとは、患者自身の血液や脂肪といった体組織を利用した治療のことで、保存療法を続けてもなかなか効果が出ない方や、手術はできれば避けたいといった方の新たな治療の選択肢となっています。
PRP療法
PRP療法とは、多血小板血漿(Platelet Rich Plasma:PRP)という血液中の血小板や白血球を濃縮して作製する液体を活用した治療法です。
血小板にはさまざまな成長因子やサイトカインが含まれており、これらには組織修復や抗炎症・除痛効果があると考えられています。(*7)
これらの成分濃度を高めた薬液を患部に注射することで、変形性膝関節症による膝の痛みなどの症状緩和を期待するのがPRP療法です。
また、PRP療法は、ゴルフのタイガー・ウッズ選手や野球の大谷翔平選手が怪我の治療に活用した治療法としても知られています。
PFC-FD™療法
PFC-FD™療法とは、先述にてご紹介したPRP療法を応用した技術で、人の血液に含まれる血小板の成長因子の働きを活用した治療法です。
成長因子には、組織修復や抗炎症、除痛などの効果が期待されます。(*7)
PFC-FD™療法の施術自体は注射であることから、体への負担も少なく済む治療法です。
また、PFC-FD™療法で使用される薬液には白血球を始めとした細胞成分が含まれないため(セルフリー加工)、注射後の痛みがほとんどないことも特徴として挙げられます。
臨床研究においては、内服薬やヒアルロン酸注射などの保存療法を行っても効果のなかった変形性膝関節症の方306膝に対してPFC-FD™療法を行った結果、12ヶ月後には60.8%(306膝中186膝)において症状の改善がみられたことが報告されています。(*7)
ただしデメリットとして、保険適用外の自由診療で行われるため、治療費は自己負担になることや、効果に個人差があることなどが挙げられます。
脂肪由来幹細胞(ASC)治療
脂肪由来幹細胞(ASC)治療は、脂肪組織由来の幹細胞を活用した治療法です。
脂肪由来幹細胞(ASC)治療によって抗炎症作用や軟骨修復などの組織修復作用が期待できます。(*8)
また、先述にてご紹介した手術などの治療法に比べ、原則入院の必要もなく体への負担が少ない治療法です。
臨床研究においては、内服薬やヒアルロン酸注射などの保存療法を行っても効果のなかった変形性膝関節症の方の107膝に対して脂肪由来幹細胞(ASC)治療を行った結果、12ヶ月後には58.9%(107膝中63膝)において症状の改善がみられたことが報告されています。(*6)
ただしASC治療は自由診療のため治療費は自己負担(保険適用外)になることや、効果に個人差があること、PRP療法やPFC-FD™療法に比べ治療費が高額であること、脂肪組織採取のため面積は小さいですが腹部などに一部切開が必要であることなどのデメリットが挙げられます。
ハイドロリリース専門外来
膝の痛みに対し、ハイドロリリースと呼ばれる比較的新しい治療法も行われるようになってきました。ハイドロリリースは、エコーを確認しながらfacia(線維性結合組織:筋膜や靭帯、支帯、腱膜、関節包、傍神経鞘など)に生理食塩水というヒトの体液とほとんど同成分の水分を注射することで、faciaの癒着を剥がす治療です。
faciaに癒着ができると、関節の可動域(曲げ伸ばしできる角度)が小さくなったり、痛みが出るようになります。ハイドロリリースを行い癒着を剥がすことで、筋肉の動きがよくなり、痛みの改善効果が見込めます。
そのためハイドロリリースは、変形性膝関節症による関節内の症状には適していませんが、周囲の筋腱が原因の痛みに対しては、たった一度の治療でも、場合によっては注射の最中から痛みがなくなるほどの効果が得られる場合もあります。
このハイドロリリースは肩こり、五十肩、腰痛に対して特に効果を発揮しやすいですが、膝に対する治療の場合、大腿四頭筋が硬くなり、大腿四頭筋や大腿筋膜張筋、内側広筋などの膝蓋骨近くに痛みがある場合でも、ハイドロリリースが治療の選択肢の一つとして検討されます。
また、ハイドロリリースは体への負担が少ない治療法ですが、局所麻酔薬を使わない場合、部位によっては注射時や注射後1週間程度、痛みを伴う場合があります。
体外衝撃波治療外来
体外衝撃波治療とは欧州を中心に広まった治療で、衝撃波を皮膚の上から患部に照射することで痛みを軽減させる治療法です。
日本ではもともと尿路結石を砕く治療として広まった治療法ですが、膝の痛みに対する治療としても行われるようになっています。
この体外衝撃波治療では患部に衝撃波を照射し、神経の痛みを感知している部分を変性・破壊、疼痛伝達物質を減少、血流を改善させることで、除痛効果が見込めます。
体外衝撃波治療には集束型と拡散型があり、集束型のほうがより高い除痛効果が見込まれ、皮膚を切らない手術として扱われます。
基本的に平均3〜5回十分な効果が見込めるとされていますが、1回でも十分な除痛効果が得られる場合もあります。※一部削除しました
治療後は、直後から痛みが改善する場合もありますが、翌日から長くて1週間程度、一時的に痛みが悪化した後に、組織修復により施術前より痛みが大幅に軽減するケースもあります。
なお、集束型の体外衝撃波治療は難治性足底筋膜炎にのみ保険適用ができる治療法です。
そのため変形性膝関節症をはじめとした膝の痛みに対して体外衝撃波治療を行う場合、治療費は全額自己負担になります。
再生医療専門外来
膝や股関節など関節の痛みに悩んでいるが、手術は避けたい方向けの治療法になります。
再生医療は、外科的な手術や薬物療法といった他の治療法と比べて、安全かつ治療の効果がより長期的かつ効果的であることが期待できます。
細胞や組織を再生することで組織損傷を起こす疾患を治療することができます。
骨粗鬆症専門外来
まとめ
膝の痛みにお悩みの方は、MRIなどの精密検査ができ、理学療法士によるリハビリが十分に受けられるなど、本記事でご紹介したような治療選択肢が幅広い整形外科をインターネットで探し、受診することをおすすめします。
単純に変形性膝関節症といっても、痛んでいる部分や程度は十人十色であり、その分だけ治療の選択肢が必要になります。
治療の選択肢が少ないと、その患者様に本当に合った治療に出会う確率もそれだけ低くなってしまいます。
当院(藤沢駅前順リハビリ整形外科)にいらっしゃる患者様の中にも、ハイドロリリースは合わなかったけれど、体外衝撃波治療なら効いたり、またその逆のパターンもあったりと、様々な治療法の提案を受けることにより、ご自身に合った治療法を見つけられた患者様が多くいらっしゃいます。
このように治療の選択肢の多い整形外科であれば、患者様の希望や、生活環境、症状に合わせた治療法をご提案することが可能です。
そのため整形外科を受診する際は、多少生活圏から離れていても幅広い治療の選択肢を提示できる整形外科の受診をおすすめいたします。
※注釈
*1…Yoshimura N, et al. (2009). Prevalence of knee osteoarthritis, lumbar spondylosis, and osteoporosis in Japanese men and women: the research on osteoarthritis/osteoporosis against disability study. Journal of Bone and Mineral Metabolism. 27, 620-628.
*2…Zhang W, et al (2008). OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis, Part II : OARSI evidence-based, expert consensus guidelines. Osteoarthritis Cartilage, 16, 137-162.
*3…津村 弘(2017).「変形性膝関節症の管理に関するOARSI勧告OARSIによるエビデンスに基づくエキスパートコンセンサスガイドライン(日本整形外科学会変形性膝関節症診療ガイドライン策定委員会による適合化終了版)」『日本内科学会雑誌』106(1), pp75-83.
*4…Treatment of Osteoarthritis of the Knee – 2nd Edition. https://aaos.org/globalassets/quality-and-practice-resources/osteoarthritis-of-the-knee/osteoarthritis-of-the-knee-2nd-editiion-clinical-practice-guideline.pdf
*5…Anwer S, & Alghadir A. (2014). Effect of isometric quadriceps exercise on muscle strength, pain, and function in patients with knee osteoarthritis: a randomized controlled study. Journal of physical therapy science, 26(5), 745-748.
小林 紘二(1994).「変形性膝関節症に対する徒手療法 ―特に関節可動域の改善について―」『理学療法学』21(2), pp.115-119.
*6…大鶴 任彦ほか(2020).「変形性膝関節症に対するBiologic healing専門クリニックの実際とエビデンス構築」『関節外科』39(9), pp.945-954.
*7…桑沢 綾乃ほか(2020).「変形性膝関節症に対する再生医療を利用した保存療法の実際-PRP・間葉系幹細胞・セルフリー療法-」『臨床スポーツ医学』37(7), pp.843-851.
※参考文献
*…小西 信幸(編)(2021).『ひざ痛 変形性膝関節症―自力でよくなる!―ひざの名医が教える最新1分体操大全』.文響社.
藤沢駅前順リハビリ整形外科へのお問い合わせ
アクセスマップ
ご要望をお気軽にお知らせください
0466-25-38120466-25-3812
診療時間 / [午前] 9:00~12:30 ※12:00 受付終了
[午後] 13:30~17:30 ※17:00 受付終了
休診日 / 土曜午後・日曜・祝日・年末年始